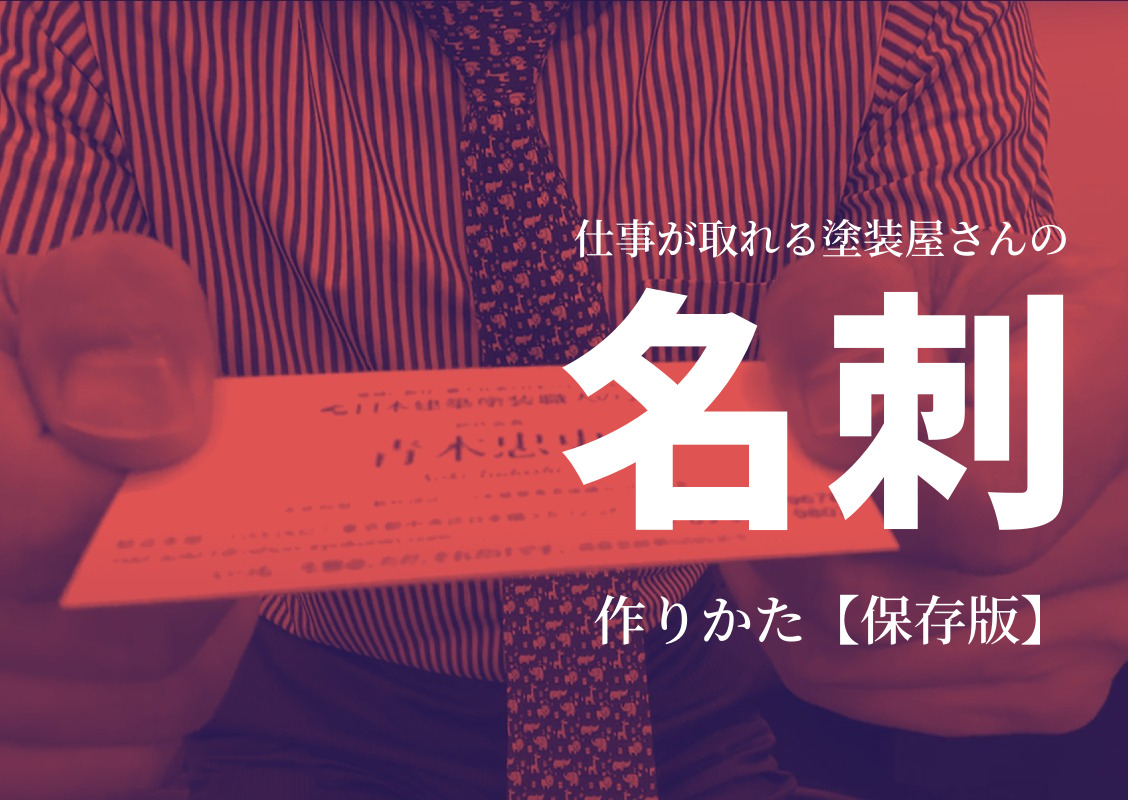
「名刺=自己紹介」の時代は終わっている…
「名刺」って、意外と、どのように作ったらよいのか、教えてくれる人も居ないし、分かりませんよね。
だから、知人や交流する業者さんと名刺交換をして「あ、これいいな~。自分も真似してみよう」と思ったりして真似をしてみるものの、実際に目だった効果はなく、ただ使っているだけという状態…。
塗装業界における”良い名刺”というのは、「お問い合わせが取れる名刺」です。
そして確かにお客様からの信頼・受注・口コミを誘発する良い名刺というは存在します。
また私の経験上、名刺経由でも問い合わせ獲得には、知名度や塗装工事の技術力にはあまり関係が無いという利点があります。
一方で、よくない名刺は、何も起きません。プラスも無ければ害も無いのです。
そこでこのページでは、これまでの700社以上の塗装店の名刺作成に携わってきたコンサルタントの私が、15年以上の経験を元に構築した『仕事が確実に取れていく塗装屋さんの名刺のつくり方』について解説をしたいと思います。
極めてオーソドックスな方法ですが、今使っている名刺との違いを意識しながら、塗装店ならではの問い合わせを生む名刺の作り方をマスターしていきましょう!
この記事の目次
1.仕事が確実に取れていく塗装屋さんの名刺・3つのポイント
まずは、『仕事が確実に取れていく塗装屋さんの名刺』の3つのポイントをご説明します。
ポイント1・・・「元請様向け名刺」と「消費者様向け名刺」を分けること
ポイント2・・・「名刺」は「チラシ」「会社案内」「ホームページ」と並ぶ会社の重要なアイテムと捉えること
ポイント3・・常時複数の名刺を作成し、効果的な名刺の改善を繰り返すこと
この3点となります。それでは、順番に見ていきましょう!
ポイント1・・・「元請様向け名刺」と「消費者様向け名刺」を分けること
1つ目のポイントは、塗装屋さんの名刺は「元請け様向け名刺」と「消費者様向け名刺」とを分けて、2種類作成することです。
なぜなら、それぞれの相手様が求める印象やイメージが違うからです。
つまり、元請様は継続的な取引を前提に、この業者は、施工品質・納期・見積を合わせて確実な工事をしてくれる業者なのか、仕事に対して不満を表現せず、従順に下請業者としての使命を果たしてくれる業者なのかという観点、いわゆるビジネスライクな観点で見ています。そのため、仕事上の信頼のおける男性を表現するように、カチッっとした名刺を作成されることがBESTです。
一方で、「消費者様向け名刺」では、一般消費者は専門分野についてを理解していないことからも「人間性」を中心に見てきます。そのため、人間性が表現できるような名刺を作成することがBESTと言えます。
| 相手 | 意思決定する際に重視されるポイント |
| 元請様(男性が多い) | 業者として、ビジネスライクとして信頼ができる業者だろうか? |
| 消費者様(住宅塗装の場合・女性が多い) | (専門分野を理解できないことからも)この人は人間として、誠実な人・職人さんなのかしら? |
【元請様向け名刺作りのポイント】
◎デザイン面でのポイント
→男性に好まれやすい比較的にカチッとしたデザイン(フォント・色彩)
◎名刺に明記する内容面でのポイント
→対応工事・対応エリア・施工実績・所有している資格などを具体的に記載すること


【消費者様向け名刺作りのポイント】※あくまで4面型名刺を元に提示しています。
◎デザイン面でのポイント
→女性に好まれやすい柔らかいデザイン(フォント・色彩)
◎名刺に明記する内容面でのポイント
→素人の女性にも分かりやすい専門用語をなるべく使わない表現方法で、「仕事に対する思い」や「沿革」などを表現すること


このようにそれぞれのお客様が求める印象に合わせて名刺を作成していくことで、それぞれのお客様からの「信頼度」が上がるという結果が出ています。
また、名刺作成においても、いろいろなデザインのスタイルがありますが、あくまで私が数多くの塗装店の名刺制作・塗装店の経営支援を行ってきた上で、経営成功軸に基づくデザインとしては、「シンプルな訴求」「シンプルなデザイン」が最も成果に近いという結果を得ていますので、上画像のようなオーソドックス・プレーンなデザインと表記を中心軸に据えているというご理解をお願いいたします。
■Q.そもそも名刺は2種類作成しても良いのですか?
また、名刺は2種類作成しても良いのですか?と時々ご質問を頂くことがありますが、結論、OKです。名刺は、必ずしも1つしか作成してはいけないという規則ははなく、2種類でも、3種類でも、4種類でも、同時に作成して構わないからです。
このようなことからも、お客様に合わせた名刺を作成していくということから、仕事がバンバン取れる塗装屋さん名刺のスタート地点となります。
お客様ごとに名刺を作成していくことが、
仕事が確実に取れていく名刺のスタート地点!
ポイント2・・・「名刺」は「チラシ」「会社案内」「ホームページ」と並ぶ会社の重要なアイテムと捉えること
2つ目のポイントは、「名刺」は「チラシ」「会社案内」「ホームページ」と並ぶ会社の重要なアイテムと捉えることです。
なぜなら、「名刺」も「チラシ」も「会社案内」も「ホームページ」も初対面の人が手にするものであり、「この会社はどのような会社なのかな?」という情報を得るためのものだからです。
そのような観点から「名刺」も以下のことを心がけて作成することが大事と言えます。
→自分の言いたいことだけを記載していないかを確認し、初対面の人に分かりやすく説明できているか?を確認してみる
◎「名刺」を渡すのは、どのようなシチュエーションなのかをあらかじめ想定しておく
→ケース①初回訪問の現地調査時 ケース②顧客様からのリピート注文時 ケース③クレーム対処時 ケース④新規取引の元請業者様とのお打ち合わせ時 など
◎「名刺」を渡したお客様を次のステップへ誘導するアクションを入れる
→ケース①不明点があれば遠慮なくお尋ねいただく ケース②会社のHPを見てもらう ケース③お知り合いの方をご紹介していただく など
意外と、ホームページ等では、上記のことを考えていても、名刺では考えていないというケースも目立ちますので、今一度、自分の名刺を見直してみましょう。
ポイント3・・・常時複数の名刺を作成し、効果的な名刺の改善を繰り返すこと
3つ目のポイントは、「常時複数の名刺を作成し、効果的な名刺の改善を繰り返す」ということです。
なぜなら、複数の名刺を使っていくうちに自分でも反応が良い名刺が分かってくるからです。
ところが、多くの方は、100枚、200枚、300枚と印刷をすると、その名刺を使い切るまで次の名刺を作成しません。
例えば、効果が無い名刺を使い切るまで何年間にも及ぶとなると、大きな機会損失(チャンスロス)を被っている可能性があるのです。
そのようなケースを想定すると、常に、2種類から3種類程度の名刺を作成して活用していくのがベストです。
常に2~3種類の名刺を作成して並行して活用していく。
すると、どれが効果が良い名刺なのか自分でも分かってくる!
2.直接の仕事が確実に取れていく名刺の作り方6のアクション
それでは、次には、「直接の仕事が確実に取れていく名刺の作り方」を具体的に6のアクションでご紹介いたします。
1つ目のアクション・・・「4面型名刺」を作成する
2つ目のアクション・・・お客様に印象づけできる会社の屋号とロゴを作る
3つ目のアクション・・・基本構成に沿って表面を作成する
4つ目のアクション・・・基本構成に沿って中面を作成する
5つ目のアクション・・・プロフィールではイメージが伝わる物語を語ること
6つ目のアクション・・・会社の成長を表現できる沿革を書くこと
それでは、順番に説明していきましょう。
2-1.『4面・縦型名刺』を作成する
1つ目のアクションは、以下のような「縦型の4面名刺」(4号長二つ折り:91×110mm)を作成することです。
★おすすめの縦型の4面型名刺(4号・二つ折り縦型:91×110mm)

・参考までに、横型の4面型名刺(4号二つ折り横型:182×55mm)はこちら。

私のおすすめは、「縦型の4面型名刺」です。
なぜ「縦型の4面型名刺」がおすすめなのかと言いますと、「一般名刺」の2倍の面積がありますが、単に2倍の情報を掲載できるということだけの効果ではなく、初対面の方に対して、必要な情報を体系的に伝えるができるということからも、面積が2倍になる以上の効果があること。
また、「横型の4面型名刺」は、面積は「縦型の4面型名刺」と同じでも、横長の形上、表現がしにくいこと。また細長くなることから心理上、不安を誘いやすいとも感じるため、どっしりとした形に見える「縦型の4面型名刺」をおすすめしています。
その他、NGな名刺とその理由を以下に挙げておきます。
【塗装店でよくあるNG名刺その1】
■一般名刺(4号(91mm×55mm)
日本での一般名刺サイズになります。

1.のポイント1で説明したとおり「元請様向け名刺」であれば、問題はないと感じますが「消費者向け名刺」では情報不足となりやすく、判断がつきにくいため、やや不適切と考えています。
なぜなら、消費者の方は、初対面時に不安感を与えてしまったら、次にお会いできる機会を与えてくれなくなるかもしれないため、できる限り、初対面では不安の払拭をしきることが大事だと考えているからです。
【塗装店でよくあるNG名刺その2】
■大きさが一般サイズとは違うサイズの名刺

時々、個性を表現するために4号サイズ以外の名刺を作成される方がおられますが、業績向上という観点に基づく効果としては、私はあまりおススメしていません。なぜなら、日本人は形が揃っていないと不安定な気持ちを感じるため、捨てられやすい感があるためです。
【塗装店でよくあるNG名刺その3】
■「4面型名刺」以上の大きさの名刺

4面以上の6面型(上図)や、8面型の名刺を制作される方もごく稀におられます。ただ、私の経験則からは「4面型名刺」以上のサイズになると、以下の特徴が出てくるからです。
・大きさ的にも名刺という感覚を外れてしまい、チラシという認識に近くなる
・大きくなれば紙質も70kg~90kg紙程度と薄くなる傾向があり、チラシと認識されやすくなる
→チラシは原則的に「売り込み」なので捨てられやすい
・スペースに無駄が生じやすくなるため、記載する趣旨に乱れが出る恐れがあり、訴求が弱くなる
上記のことからも、保存されにくくなると感じているため、塗装屋さんが6面型・8面型名刺を制作することはあまりおススメしていません。
以上のことから、「縦型の4面名刺」がBESTと考えています。
2-2.お客様に印象づけできる会社の屋号とロゴをつくる
2つ目のアクションは、「お客様に印象づけできる会社の屋号とロゴをつくる」ことです。
2-2-1.わかりやすい屋号を紹介
お客様に印象づけできる屋号とは、直感的で分かりやすい屋号を指しています。
◎塗装屋さんということがわかりやすい屋号の例
⇁◯◯塗装店、◯◯ペイント、塗装屋◯◯◯、等。「塗装」や「ペイント」が含まれているほうが良い傾向があります。
×塗装屋さんということがわかりにくい屋号の例
⇁「AtoZ」「シェル」等の名前・・・表現したい気持ちは分からないでもないですが、ストレートには伝わりにくいです。
⇁「大勝」「飛翔」「優翔」等の思い込め系の名前・・・思いは、同業者や家族には伝わりますが、お客様には伝わりにくいです。
→「△△ハウスコンサルティング」「ハウスドクター」等の変化球系の名前・・・こちらも、表現したい気持ちや趣旨は分からないでもないが、塗装屋さんとは思われにくいです。
⇁「塗り屋」などは、つけたがる方が多いですが、ありきたり感と、何の塗り屋か分かりにくさもあるので、個人的にはやや△と思っています。
近年は、情報社会でもありますし、インターネットで検索をすることからも、塗装屋さんは「塗装」という文字が入ったほうが、お客様に良い印象を与えられる傾向にあり、検索上も有利に働く傾向が強くあります。(一方で、わかりにくい屋号は、ハンディキャップマッチのように、生涯を通して経営上の苦戦を強いられることもありますので、屋号はわかりやすいことが鉄則です)
2-2-2.お客様に印象づけできるロゴマークを紹介
次には、「お客様に印象づけできるロゴマーク」を紹介しますが、その前になぜ、ロゴマークが必要なのかを説明しますね。
それは、人間は文字よりも「絵」や「画像」のほうが記憶に残りやすいという性質を持っているからです。ちなみに、記憶に残す場所は「右脳」と言われています。また「右脳」は「絵」や「画像」だけではなく、「感情」も一緒に記憶してくれるとも言われています。
つまり、「ここは信頼できそうだな♪」「ここはちょっと怪しそうだな…」などという「感情」も右脳に記憶され、お客様が忘れにくくさせるということなのです。
このような科学的根拠から逆算すると、「消費者様から見た時に、信頼のおける塗装屋さん」と、右脳的な感覚で思われるようなロゴマークを準備するということがとても大切であるということなのです。
成果を上げる「屋号」については、こちら「現役経営コンサルタントが業績改善を行なう時に使うチェックリスト48」の「屋号を変えて見ることはできないか」もお読みになってみてください。
また、これまで青木忠史会長コンサルタントがつけてきた塗装屋さんの屋号シリーズも以下にご紹介します。(実名ではなく、あくまで応用例を提示しています)
■成果を上げる屋号のヒント②(青木忠史会長コンサルタントがつけてきた屋号シリーズ)
・フルネーム系社名・・・ 青木忠史塗装店
・ニックネーム系社名 ・・・ あおちゃん塗装、あおちゃんリフォーム、塗装の青ちゃん
・感情イメージ系社名 ・・・ ハッピーペイント、ハッピーリフォーム、塗装のハッピー、ペイントワンダフル
・方言系社名 ・・・ デラキレイペイント(名古屋弁系)、ゴツペイント(関西弁系)、塗装屋けっぱれ(北海道弁)
・愛され食べ物系社名 ・・・ すももペイント、ペイントピーチ、ペイントいちご(※ご当地の食べ物がGOOD)
・愛され植物・花系社名 ・・・ バラペイント、ばら塗装店、
・愛され動物系社名 ・・・ 愛しのペイントライオン、くじらペイント、ペイントゴリラ、ペイントマンモス
・国の名前系社名 ・・・ ペイントドバイ、ペイントブリティッシュ
・星の名前系社名 ・・・ ムーンサルトペイント、ベガペイント、プレアデスペイント
・神様系社名 ・・・ イエスペイント、ペイントラムー、ペイントブッダ
このように考えていくことで、塗装屋さんでもいろいろな社名を付けていくことが出来ますし、経営が楽しくなりますね。できる限り、他店がつけていない社名で、わかりやすい名前が良いでしょう。
それでは、次は仕事が取れやすい塗装屋さんのロゴをご紹介します。
■仕事が取れやすい塗装屋さんのロゴをご紹介(これは私の経験則となります)

ポイントは以下のとおりです。
◎カッコいいロゴよりも、愛されやすいロゴが良い
◎抽象的な図形よりも、幼稚園児が好むような丸みを帯びたデザインが良い
◎できれば、愛されている動物がよい(ヘビやワニなど、多くの人に愛されにくい動物は良くないという判断)
◎社長の思い入れ・哲学を表現しているものが良い
また、上記に挙げてみた社名を応用したロゴマークを作成することも楽しいでしょう。
当ブログを運営する日本建築塗装職人の会の例
会長である青木忠史は元警察官であることから「犬のおまわりさん」がローラーを持っており、「地域の方々の安心生活を守ろう」という気概を示していること。後ろに太陽が輝いていて、地域の方々を明るく照らしている様子を表現しています。そのような塗装工事店さんの集まりが日本建築塗装職人の会なので、職人の会では、原則、以下のロゴformatを活用しています。

(こちらは日本建築塗装職人の会に著作権がありますので類似の制作はご遠慮ください)
■あまりよくない例

このように、「社長」の「思い」や「考え方」を表現しているロゴがあることで、お客様にも社員にも、その「思い」や「考え方」は伝わり、長く記憶に残り続けることになるのです。
2-3.基本構成に従って表面を作成する
3つ目のアクションは、「表面の作成」です。(あくまで一例となります)

■表面に記載する事項は以下のとおりです。
・会社名(屋号)
・ロゴ
・独自の強み
・名前
・肩書
・所有している資格
・本社所在地
・電話番号
・携帯電話番号
・直通メールアドレス
・FAX番号
・LINE QRコード
・顔写真(~上半身の写真)もしくはイラスト似顔絵
表面では、初対面の人に対して、以下のことを伝えることが大切だからです。
◎どのような会社なのか?
◎どのような人物なのか?
◎会社所在地等の連絡先
を明確に伝えること
■裏面に記載する事項は以下のとおりです。

◎次の行動を明確に促すこと
この時、カスタマージャーニー(塗装店の集客を成功に導く120のチェックポイントを参照)に則って考えていくことが大切です。
例えば、名刺を渡すシチュエーションごとに見ていくと以下のとおりです。
| 名刺を渡すシチュエーション | 次の行動 |
| ・送付する資料に同封する際の名刺では? | ・お見積依頼を促す内容を記載する ・お客様が「お見積依頼」をする前に確認したい内容へのWEBサイトページへのリンクを記載する |
| ・現地調査でお渡する際の名刺では? | ・困りごとやご相談があれば、遠慮なく来店いただくか、お電話・LINEでご相談いただく内容を記載する ・お見積を頂いたお客様が確認したい内容へのWEBサイトページへのリンクを記載する |
| ・顧客フォローでお渡しする名刺では? | ・紹介促進とリピート促進をする内容を記載する ・顧客様限定のWEBサイトページを作成し、そちらへのリンクを記載する |
それぞれのシチュエーションにおいて、次の行動が間違っていなければ、あえて、おおげさな「!」の連発や、カラフルなデザイン等にする必要もありません。
まず、1つ1つのシチュエーションごとに、促す行動を整えていくイメージを大切にしましょう。
2-4.基本構成に従って「中面」を作成する
4つ目のアクションは、「中面」の作成です。
「中面」とは、以下の画像のように見開きの面を指しています。

このように「中面」のスペースは、「小さな会社案内」と捉えて作成します。記載したい点は以下の4点です。
◎沿革
◎実績
◎代表経歴
小さなスペースですので、文字数が限られます。しかし、このような名刺を作ることを、自社を考えていくきっかけにしていくことで、自社のコンセプトが明確になり、良い表現方法が固まり、結果的に良い名刺が出来上がり、仕事が取れるようになります。
一方で、「仕事が取れる文言は何ですか?」等と質問をされる方は、本質的に間違っているのではないかとご理解ください。
名刺をつくることを、自社を考えていくきっかけにしていく。
その結果、仕事が確実に取れていくようになっていく。
以上の4つのアクションが基本のアクションとなります。
そして、次に紹介する2つのアクションはやや「応用編」となりますが、ご覧ください。
2-5.プロフィールでは、イメージが伝わる物語を語ること
5つ目のアクションは、プロフィールでは、イメージが伝わる「物語」を語ることです。
私が考える有効的な物語は以下の3つのシナリオです。
◎苦労をして育ち、親や社会のために頑張っている人生
◎平凡に育つが、欲をかかずコツコツと努力精進をし続ける人生
◎小さな頃から大きな夢を描き、その夢の実現に向かって一心不乱に頑張っている人生
上記の上で、
・具体的な施工実績(件数や有名な建造物など)
・資格の取得
・社会からの評価・表彰
・ノウハウを記した著作物
などを含めていただくことで、さらに強く「信頼」を寄せられるようになっていきます。
■イメージが伝わる物語の一例
塗装職人の父と愛情豊かな母の長男として誕生。弟の面倒をよく見る責任感の強い兄であり、学生時代は野球部にも取り組む。高校卒業と同時に塗装の道に入り、5年間の修行の後、家業の◯◯塗装店へ入社。生前の父から塗装技術を厳しく叩きこまれ、塗装の信念と◯◯塗装を支え、3代目まで繋ぐ責任を背負い◯◯年。◯◯◯賞も受賞。
母子家庭で育ち、中学生の頃から新聞配達で母を支え、卒業と同時に塗装業に携わるようになる。3年後(19歳)には親方となり現場を1人で運営し、21歳で独立。それ以来◯◯市を中心に〇〇〇棟の施工実績をはじめ、地元大手◯◯工務店との取引もある。人生を通しての夢は、ここまで育ててくれた母へ親孝行をするために母に家を買ってあげることと「日本で1番と言われる塗装職人になること!」との夢を語る。◯◯◯賞等も受賞。
2-6.会社の成長を表現している沿革を書くこと
6つ目のアクションは「会社の成長を表現する沿革を書くこと」です。
| ◯◯◯◯年◯月 | ◯◯町で代表の◯◯が体1つで塗装工事業を創業 |
| ◯◯◯◯年◯月 | ◯◯町内だけで◯◯棟の実績となる |
| ◯◯◯◯年◯月 | ◯◯市の◯◯◯の塗装工事を施工する |
| ◯◯◯◯年◯月 | はじめての塗装職人社員(親方)を採用 |
| ◯◯◯◯年◯月 | 資本金◯◯◯万円で株式会社化する |
| ◯◯◯◯年◯月 | ◯◯工務店様とお取引開始 |
| ◯◯◯◯年◯月 | 自社職人数が5名になる |
| ◯◯◯◯年◯月 | 創業10周年を達成 |
| ◯◯◯◯年◯月 | 地元の方々が安心してお問合せいただけるよう店舗を出店 |
一方で、NGな記載方法もご紹介します。
| ◯◯◯◯年◯月 | 設立 |
| ◯◯◯◯年◯月 | 法人化 |
| ◯◯◯◯年◯月 | 店舗を出店 |
どちらが信頼を感じるかは一目瞭然と思います。
3.作っただけではダメ!効果を倍増させる塗装屋さん名刺の活用テクニック
最後には、「効果を倍増させる塗装屋さん名刺の活用テクニック」をご紹介いたします。
そこで、ここでは、「社会人としての基本」からの視点と、経営的視点からの2つの点から名刺の活用方法をご紹介いたしますね。
3-1.相手様から信頼を得る名刺の渡し方と受け取り方
1つ目の名刺の効果を倍増させる活用テクニックは「相手様から信頼を得る名刺の渡し方と受け取り方」です。
そこで、まず「渡し方」からご紹介いたします。
■名刺を渡す時の基本
①両手で持ち
②社名と名前を名乗りながら(「◯◯塗装店の代表を務めております◯◯◯と申します」等)
③胸の高さで差し出します。(この時、軽くお辞儀をします)
■渡す際の注意点としては?
目下の人から名刺を差し出すのが基本ですので、元請様とお会いする場合や、お施主様とお会いする場合、いずれの場合でも、自分から名刺を差し出すことが基本となります。
(ビジネスマナーのYouTubeをご紹介:【名刺交換】元キャビンアテンダントが教えるビジネスマナー こちらもご参考にしてください)
次に、名刺の「受け取り方」をご紹介いたします。
■名刺を受け取る際の基本
①「頂戴致します」と言いながら両手で受け取ります。
*その際、相手様の会社ロゴ・会社名・お名前などに手がかからないように注意をします。
■本来、自分が先に名刺を渡さなければならないのに、相手様から先に頂いてしまった場合
①受け取ると同時に、「申し遅れました。◯◯◯塗装店の代表を務めております◯◯◯と申します」等と名刺をお渡ししてください。
最後に、名刺を頂いた後のマナーをご紹介いたします。
■頂いた名刺は?
①頂いた名刺は、商談中には、自分の左上に名刺入れの上に置いておきます。
②名刺を名刺入れにしまうタイミングは、先方様が名刺入れにしまった後か、帰り間際にしましょう。
たかが名刺と思うなかれで、名刺の扱い方は、社会では人となりを見られる礼儀作法の1つとも言えます。
つまり、マナーを知らずに扱うということは、「この人は社会人経験が少ないのかな、、」等と相手様に対して不安を与えてしまうことにもなりかねませんし、逆に、名刺の扱い方が丁寧であることで、「この方は礼儀正しい方だな。お仕事もきっちり行ってくれるのではないかな」という好印象を与えることにも繋がります。
人間は、細部で判断されやすいものですから、1人で鏡の前でイメージトレーニング等をして、いざ、お客様や元請様と名刺交換をする際には、しっかりと基本マナーができるよう、練習をしておくのも良いかもしれませんね。
名刺を扱うマナー次第で「お仕事もきっちり行ってくれるのではないかな」
という好印象を与えることもできる。
3-2.「名刺」と「ホームページ」「SNS媒体」と連携してさらに受注を増やす
2つ目の名刺の名刺の効果を倍増させる活用テクニックは、「ホームページ」「SNS媒体」を連携させてさらに受注を増やすという「考え方」です。
「2-3.の名刺を渡すシチュエーションと次の行動」にも記載してありますが、こちらは「名刺」ではなく、具体的には「ホームページ」でのページ作成や「SNS媒体」での制作等が発生してきます。
このあたりの具体的な部分は、ちなみに当ブログを運用をしている青木が会長を務めている日本建築塗装職人の会のサービスで提供していますので、よろしければ、入会をご検討いただければ幸いです。
ここでは、繰り返しになりますが、「名刺」だけではなく「ホームページ」や「SNS媒体」等と連携をして考えていくということを頭に入れておいていただければよいかと思います。
4.名刺からの一気通貫した集客を強みとする「ニッポンの塗装店」とは
ここまで、「塗装屋さんの名刺」について、いろいろなお話をしました。
結局、「名刺の作成」ではなく、「いかに、自分のお店の魅力を表現して、お客様から信頼を勝ち取るのか?」という点と、「名刺を渡すシチュエーションの次にお客様を誘導することを考えながら、名刺とホームページや媒体などを制作していくこと」が大切であるということが、伝わったのではないかと思います。
つまり、1つ目の結論は、効果的な名刺を作ることは、健全な会社をつくることに繋がっていく!ということでもあるのです。
その点、当ブログを運営する日本建築塗装職人の会では、名刺からの一気通貫した集客戦略を構築して、塗装店経営そのものを成功へと導いていく「職人の会式 塗装店経営」を「ニッポンの塗装店」というブランドで支援をしています。
具体的には以下のとおりです。
職人の会では、15年以上塗装店経営に特化してきた経営ノウハウがあるため、名刺を制作する上でも、競合他社と差別化できる自社だけの強みをしっかりと引き出し、言語化できます。そのため、名刺だけでなく「チラシ」「会社案内」「ホームページ」など全ての販促物に転用できるため、安定的な集客を実現できるようになるのです。

■ニッポンの塗装店の強み② 「名刺」を中心に一気通貫した「職人の会式 マーケティング」(以下の画像はその一部)を実践することができる
職人の会では、「名刺」以外にも、塗装店経営に必要な全ての販促物を用意しており、会員様は自由に使うことができるようになっています。
そのため、1つ1つを学びながら、自社でゼロから制作する必要がなく、現場仕事や社員育成に専念することができるので、会社がさらに強くなるのです。

これらの「職人の会式 マーケティング」は、原理原則に基づいているため、時代の変化にも左右されない強さがあります。実績として15年以上継続的・安定的に、反響獲得し続け、受注し続けることができています。そのため、加盟店の多くのお店で店舗展開や事業承継を成功させているのです。

名刺をきっかけに「職人の会式 塗装店経営」を導入し、
生涯を通した安定経営を実現しましょう。
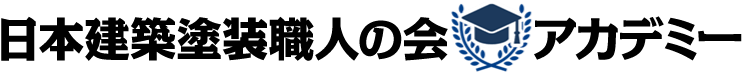
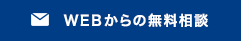









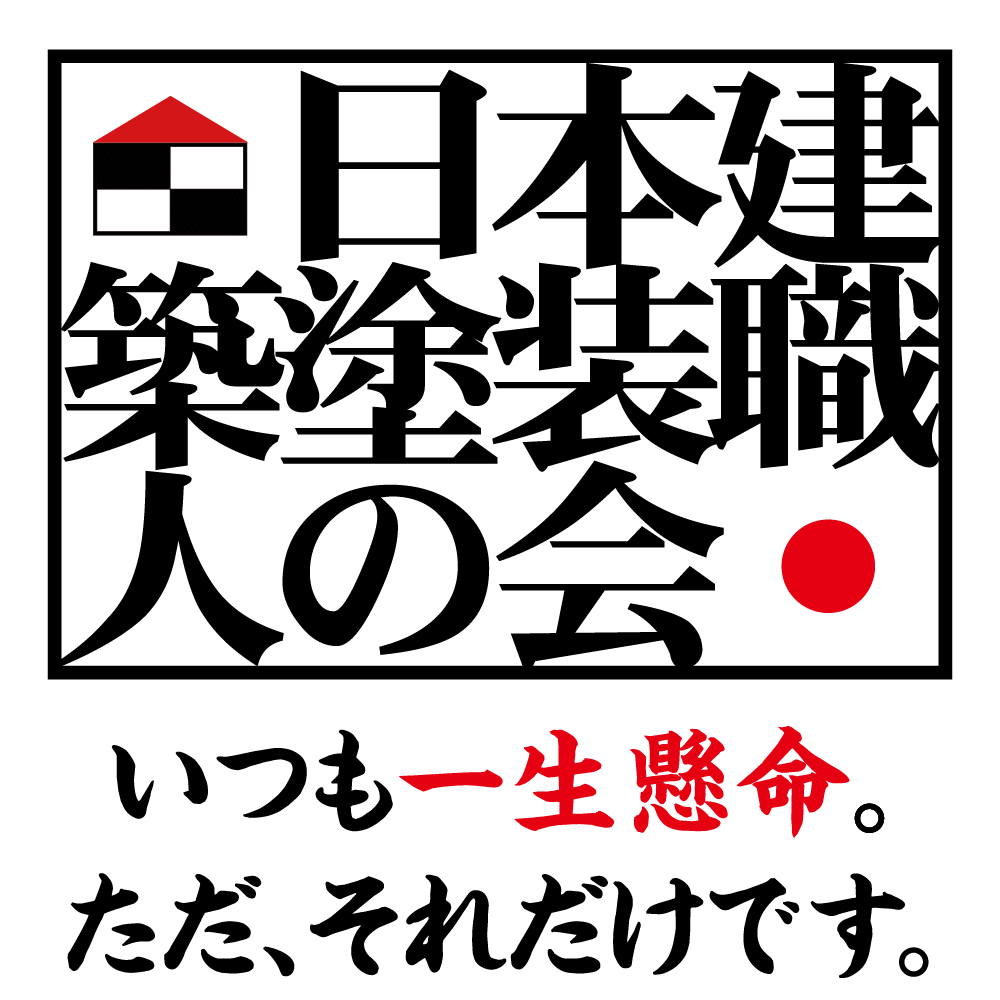
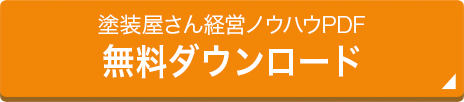
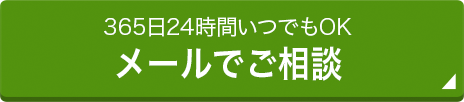
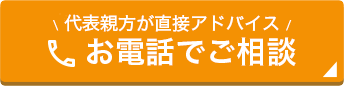
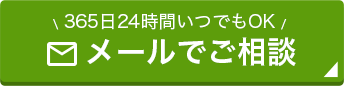
コメント